プロゼロニンとは
プロゼロニンとは、熱帯地方に自生するアネ科の植物「ノニ」に含まれていると言われていました。
ノニは、和名では「ヤエヤマアオキ」、学術名はモリンダシトリフォリア(Morinda citrifolia)という、、インドネシアのモルツカ諸島が原産の熱帯地域の植物です。
今では、インドネシアを中心に太平洋諸島、オセアニア、東南アジア、等に広く分布しています。
日本ではいつごろから健康食品としてジュースなどが出ていますが、上記熱帯地域では健康維持、スタミナ増進、病気の予防等に古くから利用されています。
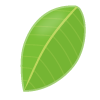
プロゼロニンの働き・効能
プロゼロニンは「ノニ」に含まれていると言われ、体内でゼロニンという成分に変化します。
ゼロニンはプロテインと結びついて、体内の修復細胞を活性化ささます。その結果、病原菌や毒素の除去や免疫機能の向上などに効果を発揮することになります。
プロゼロニンは本当にあるのか?
海外の研究者によれば、「プロゼロニンやゼロニンという物質は確認されていない・・・」という記事もありますから、上記のような効能は疑ってかかるほうが良いかもしれません。・・・というか存在自体を疑ったほうがいいでしょう。
その記事を一部抜粋すると、「ゼロニン説の論文は「再現性のない結果を掲載する雑誌」に掲載すべき代物であり、アルカロイド、ゼロニンなど明らかに科学的根拠のないものである、と断定。Heinickeのいっている事は疑問だらけであり、ノニの商業主義の門を開いただけである・・・」などと書かれています。
これは、ハワイの植物ガン研究センターのマックレチー氏という人の研究によるものだそうです。
プロゼロニンの存在と効能は、ラルフ・ハイネキー博士というアメリカの研究者が発表したものですが、その後アメリカ本土でも物議を醸したようで、結果的にウソであることを認めたようです。
当サイトでは、真意のほどはわかりませんが、このような記事が多数見られることから、あまりにも特別な効能を謳ったようなセールス記事には注意したほうが良いかと思います。
