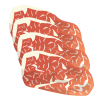
亜鉛の働き・効能
一般的な成人では、亜鉛は体内に2~4g程度存在し、多くの酵素の成分になっています。
亜鉛とは、100種類以上の酵素に含まれる必須元素で、タンパク質や遺伝情報物質DNAの合成や、糖質、脂質の代謝、インスリンの合成、免疫反応などに関与しています。要するに、新しい細胞を作るとき、この作用を進めるのが亜鉛が成分となる酵素なのです。
口内には、舌を中心に「味蕾」という味を感じる細胞の集合体が存在していますが、この味蕾は、新陳代謝が活発で10~12日のサイクルで新しく作られます。亜鉛はその形成にも不可欠な成分です。
又、最近の研究では脳機能を活性化させ、学習能力の向上に効果があるとされています
過剰摂取と不足
亜鉛が不足した場合は様々な影響がでてきます。
例えば、細胞の生成が滞り、皮膚や骨格の発育や維持が遅れたり、ホルモンの活性に影響を与えたり、あるいは傷の回復が遅れたり、脱毛や白い斑点ができたり、など様々な器官に影響がでます。
子供では成長障害を起こしますし、成人では貧血や味覚障害、皮膚炎、うつ状態などが現れ、男性では精子数を現象するなど性機能が低下します。
又、免疫機能が低下し感染症にかかりやすくなります。
亜鉛は特に通常の食生活を送る限り不足することはないのですが、インスタント食品や植物性の食生活に偏ったりした食事、あるいはアルコールの飲みすぎなどは亜鉛不足を招きます。
通常の食事では過剰症を起こすことはありませんが、大量に摂取した場合は急性中毒を起こします。
亜鉛の上手なとりかた
植物性食品に多い食物繊維やフィチン酸、加工食品に添加されるポリリン酸などは、亜鉛の吸収を妨げます。そのため、偏った食事はさけましょう。
又、アルコールのとりすぎは亜鉛の排泄量が増加しますから注意が必要です。
1日の摂取量・摂取基準
成人男性12mg未満、成人女性9mgです。
上限は35~45mgです。
亜鉛を多く含む食材
亜鉛を含んでいる食品は、魚介類や肉類、玄米、豆類、野菜、海藻、種実です。
例えば、牡蠣や牛肉、豚レバー、たらばがに、うなぎ蒲焼、ずわいがに、等です。



