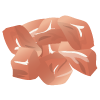コレステロールの働き・効能
コレステロールはとかく嫌われていますが、細胞膜や生体膜の構成成分として重要な役割を果たしています。神経伝達を正常にする働きもありますので、生命の維持には不可欠な成分です。
又、性ホルモンや副腎皮質ホルモン、胆汁酸、ビタミンD全躯体の原料として重要な物質です。
コレステロールの必要量としては、1日に1000~2000mgで、ほとんど肝臓で合成されますが一部は食事から摂取されます。
コレステロールは血液に溶け込んで体内の組織に運ばれます。その後リン脂質とアポタンパク質におおわれて粒子になり血液に入ります。これがリポタンパク質です。
血液中のコレステロール値が低下しすぎると、細胞膜や血管が弱くなったり、免疫力が低下します。又、脳出血や癌(がん)を起こしやすくなります。
悪玉コレステロールと善玉コレステロール
リポタンパク質は4種類に大別されます。
そのうち、LDL(低比重リポタンパク)は増えすぎた場合血液中で血管壁にこびりつき動脈硬化の原因になります。これが「悪玉コレステロール」です。
一方HDL(高比重リポタンパク)は血管にこびりついたコレステロールや余ったコレステロールを肝臓に運ぶ役目をします。そのため血管がきれいになりますので「善玉コレステロール」と呼ばれます。
この、「善玉コレステロール」であるHDLを増やすためには動物性脂肪や高コレステロール食品を減らし、食物繊維やEPA・DHAを含む食品を多くとるようにしましょう。
酸化型のLDL
血液中のLDLコレステロールが過剰になると、高LDLコレステロール血症を招きます。増えすぎた場合は、血管壁に入り込みそれが酸化され、「酸化型のLDLコレステロール」に変わります。
この酸化型のLDLが血管壁にどんどん溜まってくると動脈硬化が進行し、いずれは心筋梗塞や狭心症などの脳血管疾患や心疾患などの可能性が高まります。
コレステロールの上手なとりかた
コレステロールの吸収を抑制する食物繊維が多い食品(野菜やきのこ、海藻、等)などを十分にとるようにしましょう。ちなみに野菜は1日350gが目標値です。
調理に使用する油は、総コレステロール値を下げ、HDLを下げないオレイン酸の多いオリーブオイルなどがおすすめです。
HDLを上昇させる作用があるDHAやIPA(EPA)が多い背青魚(いわしやさんま、等)週に1回は摂るようにしましょう。
飲酒は悪いイメージがありますが、適量のアルコール(日本酒で1日1合以下)ではHDLを下げる効果があります。多量の飲酒ではLDLを上昇させます。
コレステロールを多く含む食材
するめ・生剣先いか・鶏卵や鶏卵黄身・うなぎ蒲焼・・など
コレステロールを減らす食材
貝類をとると含まれるタウリンが肝機能を強化してくれます。海藻に含まれるアルギン酸もコレステロールを消費してくれます。さらに、高酸化作用が高いβカロテンやビタミンc・ビタミンE・ポリフェノールなどもとると良いでしょう