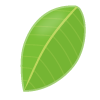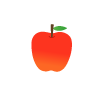酢酸とは
酢酸は食酸の酸味成分で、体内ではクエン酸になります。
そしてクエン酸サイクルにより、糖質が効率よく代謝されエネルギーになっていきます。このクエン酸サイクルが正常に廻らなければ体脂肪が増加してしまうことになります。
酢酸は生体内で活性化体であるアセチルCoA(アセチル補酵素A)としてさまざまな役割を果たす。アセチルCoAは活性酢酸とも呼ばれる酢酸のチオエステル体であり、CoASHはよい脱離基として働くため酢酸そのものよりも置換反応が起こりやすい。・・・・生成したアセチルCoAはクエン酸回路でのエネルギー生産や、脂肪酸の合成、メバロン酸経路によるテルペノイド・ステロイドの生合成などに利用される。クエン酸回路による代謝では、酢酸は最終的に二酸化炭素と水になる。
引用先:wikipedia-酢酸
酢酸の働き・効能
酢酸はクエン酸サイクルにより疲労物質を取り除きます。
血液も弱アルカリ性に保たれますので、体調も整われることになります。
さらに、殺菌作用により有害細菌が腸に入るのを防ぐ効果もありますし、血行を良くしますので冷え性、肩こりなどにも有効です。
酢酸の用途
酢に使用される酢酸はそれほど多いものではなく、主に化合物を作る際に試薬として利用されています。
又、調味料や防腐剤などにも利用されます。