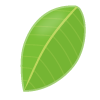カロテノイドとは

カロテノイドとは、動植物に存在する脂溶性の天然色素で、その種類は大変多く、600種類にもおよぶといわれますが、カロテン類とキサントフィル類に分類されます。
体内でビタミンAの働きをするβカロテンはカロテン類の代表格です。他のカロテン類としては、カプサイチンやキサントフィル類、リコピンなどがあります。
尚、必要に応じて体内でビタミンAに変換されるものを「プロビタミンA」といいます。
動物性食品のカロテノイド
カロテノイドは動物性食品にも存在します。
一例としては、かにやえびの赤い色であるアスタキサンチンという色素はカロテロイドの一種ですし、卵の黄身はルテインという色素です。
カロテノイドの働き・効能
カロテノイドは全て抗酸化作用があり、ガンを防いだり心臓病や脳血管障害、動脈硬化などの生活習慣病や老化(アンチエイジング)、目の病気などにも有効です。
いくつかのカロテノイドの種類と効能を紹介してみましょう。
β-カロテン
プロビタミンAの中でも食品中に最も多く含まれ、ビタミンAへの変換率も最も高いものです。視覚機能、皮膚や粘膜細胞を正常に保ち、免疫機能の維持などに効果を発揮します。
かぼちぁや小松菜、にんじん、ほうれん草などに多く含まれます。
アスタキサンチン
強力な抗酸化作用があり、免疫力を高めます。
さけやかに、えび、おきあみなどの魚介類や海藻類に含まれる赤い色素です。
フコキサンチン
抗酸化作用以外に、脂肪の燃焼を促進し内臓脂肪を減らす働きもあります。
わかめやもずく、ひじきまどの褐藻類に含まれる赤褐色の色素です。
ルティン
目の網膜の黄斑にあるカ炉手のカロテノイドで、紫外線を吸収して活性酸素の害を抑制し、黄斑変性や白内障を予防します。
とうもろこしや卵黄、豆類に含まれる黄色の色素です。
ゼアキサンチン
ルティン同様目の網膜の黄斑にあり、黄斑変性、白内障の予防効果が期待されます。
とうもろこしや卵黄、レバーなどの黄色から橙色の色素成分です。
β-クリプトキサンチン
プロビタミンAでみかんやオレンジなどの柑橘類、とうもろこしなどに多く含まれます。
カプサイチン
強力な抗酸化力でLDLコレステロール(悪玉コレステロール)の酸化を防ぎます。
赤ピーマンや赤唐辛子に含まれる赤い色素です。
α-カロテン
プロビタミンAの仲間で、βカロテンより強い抗酸化作用があります。
にんじんやかぼちゃなどの赤黄色野菜に含まれます。
γ-カロテン
プロビタミンAの仲間で、体内での変換率はαカロテンよりも低いのが特徴です。
かぼちゃやあんず、とまとなどの緑黄色野菜に含まれます。
リコペン(リコピン)
βカロテンより強い抗酸化力があり、動脈硬化を抑制します。脂溶性の赤色の色素で、完熟とまとn多く含まれ、すいかなどにも含まれます。
上手なとりかた
このようにカロテロイド類の抗酸化作用は、一種類だけをとるよりも複数のものをとったほうが効果的です。
複数のものをとるためには、サラダにしても色とりどりの野菜や果物を組み合わせるようにしましょう。
又、油に溶けやすいので油と一緒にとると吸収率が高まります。
カロテロイドの多い食品とは
カロテロイドには多くの種類がありますが、大別するとカロテン類とキサントフィル類になります。
尚、カロテン類はアルコールに溶けなく、キサントフィル類はアルコールに溶けるのが特徴です。
カロテン類
- α-カロテン・・・緑黄色野菜
- β-カロテン・・・緑黄色野菜
- γ-カロテン・・・緑黄色野菜
- リコピン・・・とまとやスイカなど
キサントフィル類
- ゼアキサンチン・・・マンゴーやパパイヤなど
- カプサイチン・・・赤唐辛子、赤ピーマンなど
- ルテイン・・・きゃべつ、ほうれん草、そばなど
- フコキサイチン・・・海藻類
- クリプトキサンチン・・・とうもろこし、みかんなど
関連記事