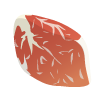脳・神経の働きと病気
脳や神経系はは、人が生活するうえで最も重要な働きをしていますが、酸化ストレスに大変弱いという特徴を持っています。
脳の病気としては、脳卒中や認知症が代表的なものとしてあげられます。
脳卒中は過度の飲酒や過労が原因となり引き起こされ、酸化ストレスで血管が壊れた場合は再生はできませんが、リハビリにより機能回復が可能です。
認知症は高齢者に比較的多い病気ですが、これは軽度の脳梗塞を繰り返すことでその症状が進行していく「脳血管性認知症」や、脳が萎縮していくアルツハイマー病などがあります。
これらの治療には画期的なものは無いと言われているのが実情ですが、近年では研究が重ねられ、有望な治療法がいくつか期待されているようです。
脳卒中を予防する食習慣
脳卒中といっても毎日に食習慣の積み重ねで発症リスクをかなり低くできるのです。
そのためには、高脂肪・高エネルギーという食事を改め、野菜や良質のタンパク質を中心に、塩分の少ない食事を心がけることです。大量の飲酒も脳卒中の危険性を高めます。なかでも、脳出血とくも膜下出血は、危険性が飲酒の量と比例するといわれます。
体内の水分が少ないことも良くありません。血液が濃くなり血栓ができやすい状態になりがちです。水分を充分に補給し、食生活の改善と適度な運動を心がけることで相乗効果が期待できます。
食材選びのポイント
主食は食物繊維が多い玄米がおすすめです。玄米には白米の4倍以上の食物繊維が含まれます。
主菜には青背魚のDHAをとるようにしましょう。青背魚には動脈硬化を抑制するタウリンが豊富ですし、DHAには血栓防止効果があります。
他にも、グリーンアスパラガスに含まれるルチンは毛細血管を強化し、高血圧を予防する効果がありますし、カリウムが塩分を排出してくれます。又、抗酸化成分が強い生姜のショーガオールは体を温めてもくれます。
認知症を予防する食習慣
認知症の原因ははっきりとは解明されていません。
認知症の一つである脳血管性認知症は脳血管障害が原因なので、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの病気の予防法と同様の対策が必要です。
アルツハイマー型認知症の予防には、抗酸化作用のあるビタミンEや青背魚のDHA・IPA、イチョウ葉エキスのギンコライド、魚介類に含まれる赤い色素のアスタキサンチンなどが有効だといわれています。さらに、適度な運動や活発な精神活動を維持することも重要です。
食材選びのポイント
大豆や大豆製品には、記録力や集中力を高める大豆レクチンが含まれています。さらにコレステロールが血管に付着するのを予防します。
青背魚のDHA・IPAは血栓を予防します。鮭には抗酸化作用の高いアスタキサンチンを豊富に含みます。
ビタミンCやEの抗酸化作用が認知症の予防につながることがわかっています。
| 栄養成分についての知識 栄養成分についてのの詳しい解説は 下記のリンクをご覧ください。 スポンサーリンク |
脳・神経の病気に有効な栄養素
脳卒中や脳血管認知症には、塩分と脂肪の制限が必要とされます。
脳梗塞には、食物繊維や魚介類を豊富に摂取するとコレステロール値を下げる効果がありますので有効です。
アルツハイマーには、ビタミンEやB1などが有効といわれますが、まだ不明な点が多いようです。
脳出血には、タンパク質やミネラル、ビタミンなどをバランスよくとることが重要です。
血栓を予防する野菜
- 薬理効果の高い野菜・・・れんこん・あすぱら・せろり・ししとう・ねぎ・エシャレット・青じそ・あしたば・・・など
- 効果が高い野菜・・・しゅんぎく・わけぎ・大根の葉・あさつき・にんじん・ピーマン・チンゲンサイ・・・など
- 効果がある野菜・・・もやし・ブロッコリー・大根・グリンピース・三つ葉・・・など