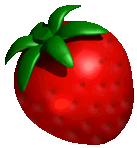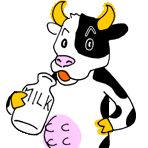特定保健用食品(トクホ)・栄養機能食品というものがあるのは既にご存知だと思います。
特定保健用食品とは、一般的に「トクホ」と呼ばれています。
従来健康食品と呼ばれるものは、自主的な安全基準にしたがい製造されていました。
そのため品質が十分でないものや、薬と間違えるよな表現をしたり、過剰な広告で売り出すようなあやしいものもありました。・・・今もあると思います。
これでは健康被害にあったり、場合によったら薬事法にひっかかるかも知れません。
そこで厚生労働省は、国民が正しい選択ができるように、科学的根拠があって健康を促進させる特定の機能があると認められる食品には、健康への効用を表示できる制度を設けました。
これが「特定保健用食品」と呼ばれるものです。
厚生労働省のページでは、「からだの生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つことを助けたり、おなかの調子を整えるのに役立つなどの特定の保健の用途に資する旨を表示するもの」と表示されています。
特定保健用食品(トクホ)には、上記のように健康維持増進に役立つ成分が含まれています。
体調を整えたいような人や、生活習慣病を予防したいような人は利用してみるのも良いでしょう。
スポンサーリンク
栄養機能食品とは?
さらに、新たな保険機能食品制度が導入されました。従来の特定保健用食品(トクホ)に加え、「栄養機能食品」というカテゴリーです。
栄養機能食品とは、不足しがちな栄養成分の補給を目的にした食品で、一定の条件を満たせば、含まれる栄養素がどんな機能をもつかを表示できます。そして、「注意喚起表示」も義務付けられています。
例えば、「本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。〇〇の摂りすぎは、〇〇の吸収を阻害するおそれがありますので、過剰摂取にならないよう注意してください。1日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。」というようにです。
この栄養機能食品も、医薬品と間違えるような表示方法や、誇大広告は禁止されています。
現在では、特定の栄養素(ビタミン・ミネラル)が対象になっていますが、今後その種類は増加していくと思われます。
サプリメントを選ぶ際には参考にすると良いでしょう。
特別用途食品
これは、「病者用、乳児用、妊産婦用などの特別の用途に適する旨の表示をする食品」です。
病気や乳幼児、妊産婦、などの人の発育や健康保持・回復のためなど、特別の用途に適するという表示が認められています。
これも国の許可を受ける必要があります。