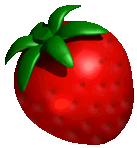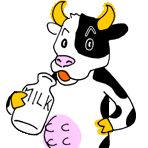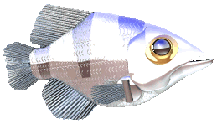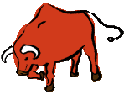海藻を食べて健康になろう!!

海藻と一言でいってもその種類はかなりの数があるのです。それを大別してみると、褐藻類・紅藻類・緑藻類という3つの種類に分けることができます。
日ごろ耳にするもので見てみると、褐藻類には各種のコンブ類、ひじき、もずく、ホンダワラ、紅藻類は浅草海苔や天草、緑藻類では青海苔やアオサノリ、などがあります。他にも数十種類の海藻があるのですが、後はほとんど聞いたことがないものが多く、食べて美味しいのか、食べられるかどうかも良くわかりませんし、このサイトとはあまり関係ないのでこの話はこのへんにしておきます。
さて、海藻に含まれる栄養素とその効能ですが、もちろん海藻にも必要な栄養素は豊富に含まれています。
含まれている栄養素の種類としては、ビタミン、ミネラル、食物繊維などで、不足しがちな鉄分やカルシウムも豊富に含んでいます。そして、何より低カロリーですから言うことありません。
これらの栄養素の効能としては、ビタミンやミネラルは糖質・タンパク質・脂質が十分に力を発揮できるように潤滑油としての働き、食物繊維は整腸作用や免疫力を高めること、鉄分は貧血の予防、カルシウムは骨や歯を作ったり、消化酵素を活性化させる働き、等かなり多くのものがあります。
特に、海藻に含まれる食物繊維は「水溶性食物繊維」で、腸内のコレステロールを吸収して排出する効果があります。さらにこの水溶性食物繊維の主成分はフコイダンとアルギン酸という優れた薬効を持っています。
フコイダンとはコンブなどのねばねば成分のことです。これは、巷でガンの特効薬とか、末期がんでも効くなどと、あやしいキャッチフレーズでかなり高い値段で売られているのを見かけますが、実は免疫力を活性化させる成分なのです。
フコイダンは「抗腫瘍作用」が、マウスの実験などで確認されているらしく、代替医療では抗がん剤としての利用も始まっているようです。ちなみに、代替医療とは食事療法や気孔、整体などを指し、西洋医学以外の治療法のことです。
海藻類を選ぶときのポイントですが、色やつや、そして厚みを見て選びましょう。
保存するときは、湿気と高温を避けるために、密閉容器に入れ冷蔵庫で保存しましょう。
スポンサーリンク
各種の海藻と栄養成分
加工品